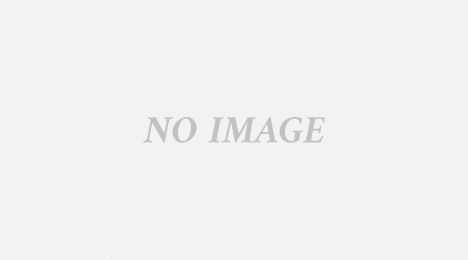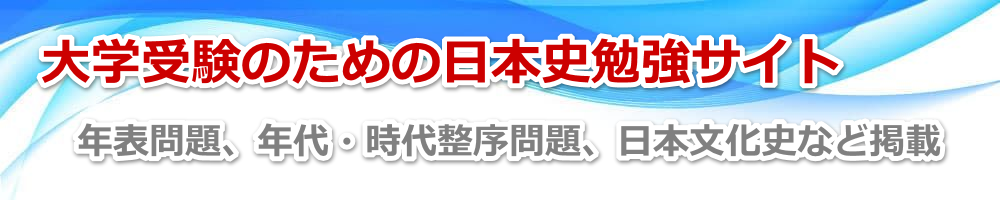
大学受験のための日本史勉強サイト
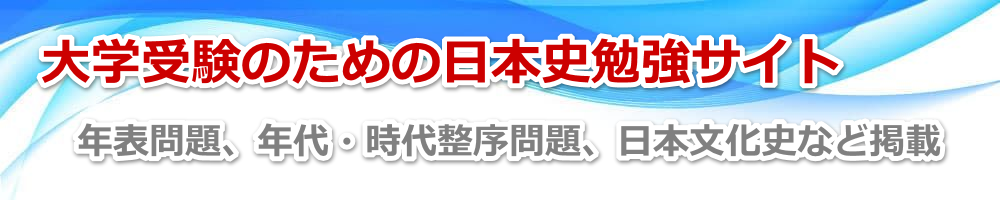
日本史Bの人物問題集(田沼意次)
【問題】田沼意次に関する説明で正しいものを選べ。
- (A)新田開発を進めるため旧里帰農令を出し、農村に帰ることを奨励した
- (B)後に世直し大明神と呼ばれる佐野政言に江戸城内で刺殺された
- (C)仙台藩医の工藤平助の進言により蝦夷地の開発やロシアとの交易を調査した
ヒント:田沼意次が生きた時代
| 1721年 | 目安箱を設置 |
|---|---|
| 1732年 | 享保の飢饉 |
| 1758年 | 宝暦事件 → 竹内式部が尊皇論を説いて追放される |
| 1774年 | 「解体新書」出版 → 杉田玄白、前野良沢による |
| 1782年 | 天明の飢饉 |
大学入試「日本史B」での田沼意次の重要ポイント
- 老中
- 1720年〜1788年(江戸時代中期)
- 10代将軍家治の時代に実権を握り「田沼時代」を築く
- 経済活動を活発にすることで幕府の財政再建を目指した
- 新田開発のために印旛沼や手賀沼の大規模な干拓工事を進める
- 新井白石の長崎新令を緩和して貿易を促進し、銅や俵物の輸出した
- 俵物とは…俵詰めで発送される海産物(いりこ、ほしあわび)のこと
- 定量計数銀貨である南鐐弐朱銀(なんりょうにしゅぎん)を鋳造
- 南鐐とは…上質な銀のこと
- 賄賂や縁故人事の横行で批判され失脚した
【正解】
(C)仙台藩医の工藤平助の進言により蝦夷地の開発やロシアとの交易を調査した
- 田沼意次は、この進言により最上徳内を蝦夷地に派遣している
- 佐野政言に江戸城内で刺殺されたのは、若年寄となっていた息子の田沼意知
- 旧里帰農令は、田沼意次死後の寛政の改革で出されたもの