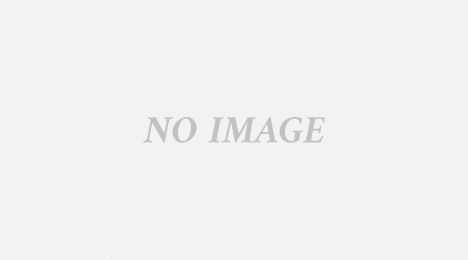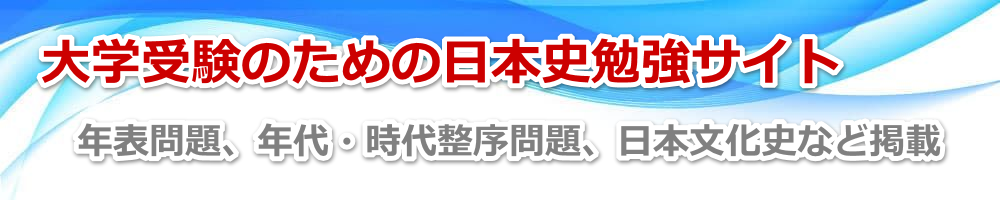
大学受験のための日本史勉強サイト
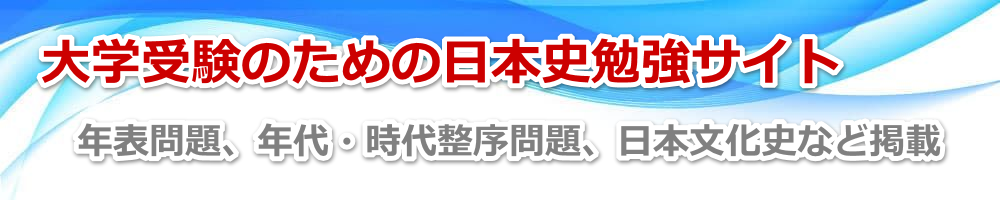
ネットでできる日本史Bの人物問題集(本居宣長編)
【問題】本居宣長に関する説明で間違っているものを選べ
- (A)「国意考」にて、日本古来の思想への復古を主張した
- (B)源氏物語の注釈書では「もののあはれ論」を展開している
- (C)古事記についての解説書「古事記伝」を執筆した
ヒント:本居宣長が生きた時代
| 1772年 | 田沼意次が老中になる |
|---|---|
| 1774年 | 杉田玄白「解体新書」を翻訳 |
| 1776年 | 平賀源内「エレキテル」を製作 |
| 1782年 | 天明の飢饉 |
| 1792年 | ロシアのラスクマンが根室に来航 |
大学入試に出る本居宣長
- 国学者、医者
- 1730年〜1801年(江戸時代中期〜後期)
- 古事記についての研究をすすめ、解説書となる「古事記伝」を執筆
- 古事記のほかにも万葉集など日本の古典を研究し、「国学」の発展に寄与
- 源氏物語の注釈書「玉の小櫛」では、「もののあはれ論」を展開している
- 「秘本玉くしげ(ひほんたまくしげ)」では、政治経済論を論じている
- 宣長の国学の研究は、復古神道(ふっこしんとう)へと発展していく
- 復古神道とは、仏教や儒教の影響を受ける前の日本古来の信仰に立ち戻ろうとする考えで平田篤胤(ひらたあつたね)らが広めた
- 復古神道は明治維新の尊皇論とも結びついていくこととなる
【正解】
(A)「国意考」にて、日本古来の思想への復古を主張したが間違い
- 「国意考」を執筆したのは賀茂真淵(かものまぶち)
- 本居宣長は、賀茂真淵を師とあおいでいた
- 本居宣長の著書では「古事記伝」「玉の小櫛(たまのおぐし)」などが有名