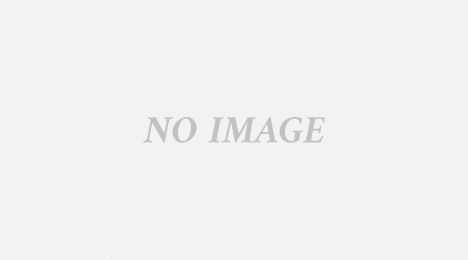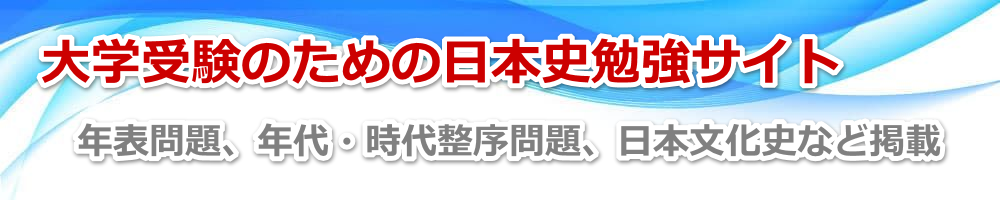
大学受験のための日本史勉強サイト
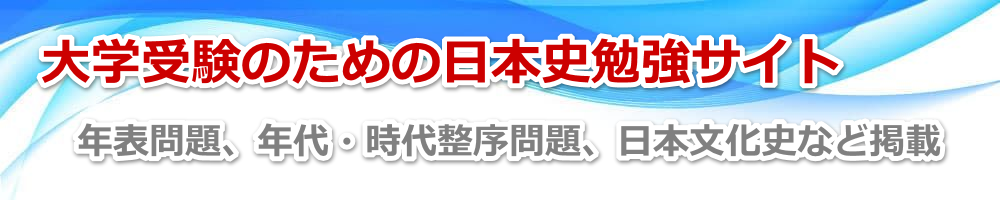
日本史Bの人物問題集(松平定信)
【問題】松平定信に関する説明で正しいものを選べ。
- (A)上げ米を実施して、石高1万石につき100石の割合で米を上納させた
- (B)旧里帰農令を出し、江戸の没落農民に対し資金を与えて帰農を奨励した
- (C)財政再建のため上知令により江戸・大阪周辺を幕府の直轄地にしようとした
【応用問題】上記の選択肢で松平定信でないものは、誰によるもののことか述べよ
ヒント:松平定信が生きた時代
| 1767年 | 田沼意次が側用人になる → 72年には老中となり「田沼時代」に |
|---|---|
| 1782年 | 天明の飢饉(〜87年) → 東北地方を中心に多数の餓死者が出る |
| 1783年 | 浅間山の大噴火 |
| 1798年 | 本居宣長「古事記伝」完成 |
| 1825年 | 国船打払令 |
大学入試「日本史B」に出る松平定信のポイント
- 老中
- 1758年〜1829年(江戸時代)
- 徳川8代将軍吉宗の孫
- 白河藩主としての功績を評価され老中に抜擢される
- 徳川家斉(11代将軍)の下で寛政の改革を実行
- 飢饉に備えて各地に社倉や義倉を作らせ穀物を蓄えさせた(囲米)
- 「寛政異学の禁」により儒学の中で朱子学以外を禁止した
- 旗本・御家人救済のために「棄捐令(きえんれい)」により札差に借金を放棄させた
- 札差(ふださし)とは…旗本・御家人に支給される米の仲介をするもの
- 出版統制令により政治風刺や風俗を乱す書物を取り締まった
- 自叙伝「宇下人言」は「定信」の2文字を分割して付けた書名
【正解】
(B)旧里帰農令を出し、江戸の没落農民に対し資金を与えて帰農を奨励した
- 旧里帰農令は、松平定信の寛政の改革で出されたもの(同様の「人返しの法」が水野忠邦による天保の改革で出されている)
【応用問題の正解】
- (A)上げ米を実施 → 徳川吉宗(8代将軍)
- (C)上知令 → 水野忠邦(老中)
松平定信の寛政の改革は、徳川吉宗の享保の改革に倣ったもの