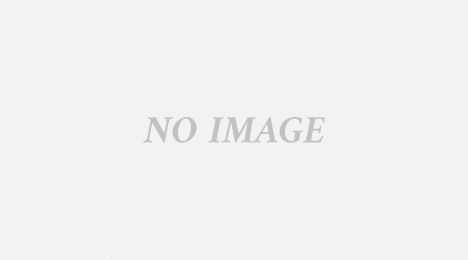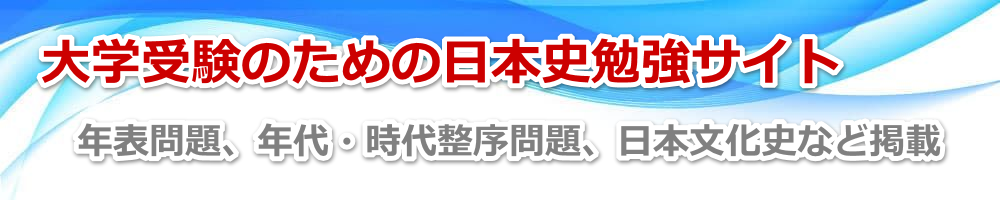
大学受験のための日本史勉強サイト
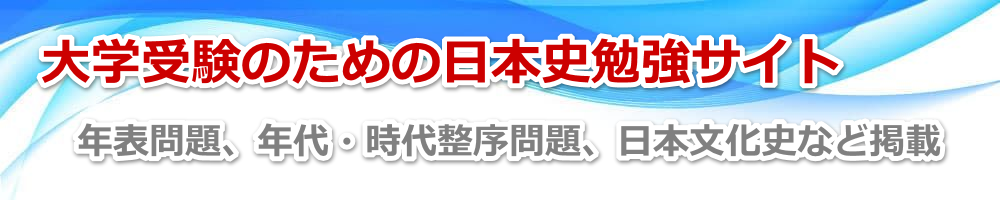
日本史Bの人物問題集(新井白石)
【問題】新井白石に関する説明として正しいものを選べ
- (A)万葉集の注釈書「万葉代匠記」を完成させた
- (B)海舶互市新例を出し、長崎貿易における金銀の流出を抑えた
- (C)徳川綱吉により大学頭に起用され、儒学を仏教から分離させた
【応用問題】上記の選択肢で新井白石でないものは、誰のことか述べよ
ヒント:新井白石が生きた時代
| 1669年 | シャクシャインの戦い |
|---|---|
| 1674年 | 関孝和「発微算法」→代表的な和算書で、筆算による代数計算法を記したもの |
| 1685年 | 生類憐れみの令 |
| 1689年 | 松尾芭蕉「奥の細道」→元禄文化と呼ばれるものの一つ |
| 1716年 | 享保の改革(〜45年)→8代将軍吉宗による改革 |
元禄文化はほかに井原西鶴「好色一代男(1682年)」近松門左衛門「曽根崎心中(1703年)」など
大学入試「日本史B」に出る新井白石のポイント
- 朱子学者、政治家
- 1657年〜1725年
- 6代将軍家宣、7代将軍家継の下で侍講を務めた
- 正徳の治を推進
- 閑院宮家を新設
- 朝鮮通信使の待遇を簡素化
- 朝鮮国書内の将軍の称号を日本国大君殿下から日本国王に改めさせた
- 金の含有率を高めた正徳小判を鋳造
- 海舶互市新例(長崎新令、正徳新令)にて金銀の海外流出を防ぐために貿易を制限
- 著書に「読史余論」「古史通」「折たく柴の記」など
- 読史余論…徳川政権の正当性を述べた書で6代将軍家宣に進講した内容
- 古史通…日本書紀について合理的解釈を下したもの
- 折たく柴の記…自伝
【正解】
(B)海舶互市新例を出し、長崎貿易における金銀の流出を抑えた
- 海舶互市新例は長崎新令、正徳新令とも呼ばれる
- 新井白石は6代将軍家宣、7代将軍家継の下で正徳の治と呼ばれる政治を行っている
【応用問題の正解】
- (A)万葉集の注釈書「万葉代匠記」を完成させた → 契沖
- (C)徳川綱吉により大学頭に起用され、儒学を仏教から分離 → 林信篤(鳳岡)
「万葉代匠記」は契沖が徳川光圀の要請を受けて作成したもの。
新井白石は日本書紀について合理的解釈を下した「古史通」を記している。