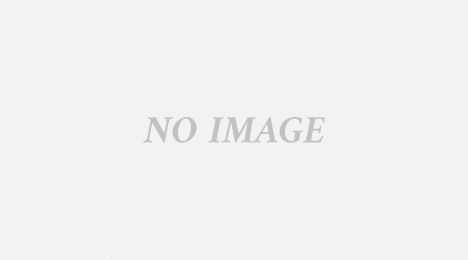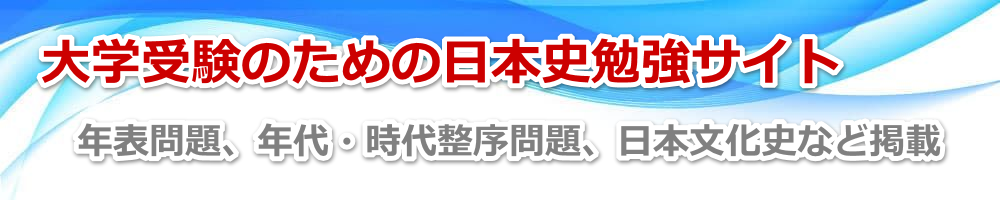
大学受験のための日本史勉強サイト
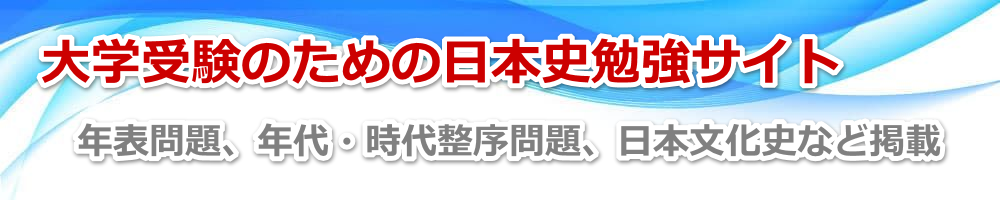
センター試験日本史Bで出題された正中の変、嘉吉の変
平成27年のセンター試験日本史Bの第3問で「正中の変」と「嘉吉の変」が出題されました。
いずれも高校の教科書にも掲載されている出来事です。
紛らわしい別のナントカの変と混同しないように覚えておきましょう。
正中の変について
正中の変の読み方は「しょうちゅうのへん」です。
鎌倉時代の末期1324年の出来事です。
鎌倉幕府が滅亡したのが、1333年ですから、その9年前。
後醍醐天皇が討幕計画を立てたものの失敗したのが正中の変です。
これとセットで覚えておきたいのが元弘の変(げんこうのへん)。
正中の変の7年後1331年に起きた出来事。
内容は同じ。
後醍醐天皇による討幕計画。
結果も同じで失敗に終わります。
これにより後醍醐天皇は隠岐に流されることとなります。
その後、隠岐を脱出した後醍醐天皇と足利高氏らが鎌倉幕府を滅亡させました。
嘉吉の変について
読み方は「かきつのへん」。嘉吉の乱と呼ばれることもあります。
こちらは室町時代の1441年に起きた出来事。
有力守護だった赤松満祐(あかまつみつすけ)が足利6代将軍義政を暗殺したのが嘉吉の変です。嘉吉は人の名前ではありません。元号です。
その後、赤松は幕府軍に討たれ敗死しますが、これ以降、足利将軍の権力基盤は弱まり、応仁の乱へつながっていくことになります。
ちなみに、足利15代将軍の中で暗殺された将軍は6代義政のほかにもう一人います。
13代将軍の足利義輝(よしてる)です。
こちらは永禄の変(えいろくのへん)と呼ばれ、1565年の出来事です。